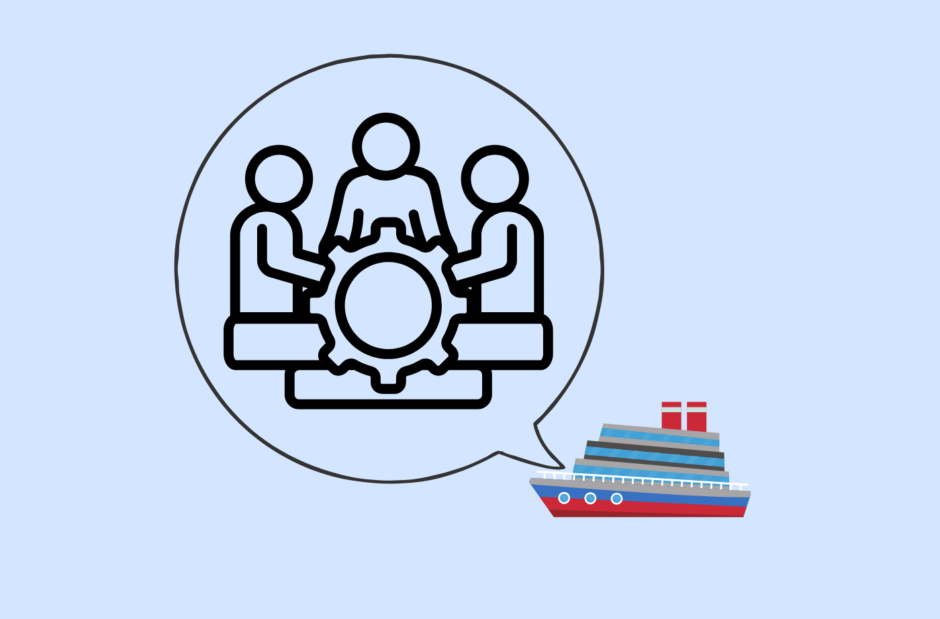船の運航のマネージメント、いわゆる『船舶管理』の話です。
「船舶管理」という言葉を聞いても、皆さんは違和感がないと思います。しかし、私が入社したころには「船舶管理」という言葉はあまり聞き慣れない言葉でした。当時の海運会社では、本社機構の中に船舶管理業務が存在しており、「海務部」、「工務部」、「船員部」という社内の部門が船舶の管理業務である航海技術、積荷技術、船舶監督、資材調達、船員配乗等をそれぞれ分担して行っていました。直接、海運会社が船を管理する、いわゆる「直接管理」の時代でした。そのため統合的な「船舶管理」という言葉を使用していませんでした。
それが海運不況を契機に制度改革が進み、本社から切り離した船種毎の船舶管理会社を作り、その管理会社が船舶の管理業務を行うという「間接管理」という制度になりました。船種は主にコンテナ、自動車、ドライ、タンカー、LNGの5つに区分されます。船舶管理という概念では日本は後進国ですが、欧州ではかなり昔より「船舶管理」というノウハウを商売にする企業が存在し、優秀な人材を確保して船舶管理会社として世界中の船を相手に管理業務の商売を行っていました。
今述べたように船を管理する形態は「直接管理」と「間接管理」の2つに分類することができます。昔の日本の海運会社では多くの船を「直接管理」していたのです。日本の荷主さんのために外国からエネルギー資源や原材料を運ぶ、あるいは日本の荷主さんのコンテナや雑貨を輸出入するために船舶を運航するのが主流でした。従って自社で管理し、自社船員を配乗し、自社運航する船が主体となっていたのです。自社の運航船舶を自社で直接管理していました。
ところが、時代が移って三国間輸送や多くの海外の荷主を相手にするようになりました。また、国際競争力を高めるために安価な船を運航せざるを得なくなり、自然と管理会社は海外が主体となりました。さらに3rd Partyという自社と関係のない船舶を使用せざるを得なくなってきたために間接管理という手法が主流となり現在に至っています。
しかし、この間接管理には重大な欠点があります。それは直接、本社が船に携わる機会が激減したため、船会社スタッフが現場を知らない、現場状況を把握できなくなっているという問題です。それでは現場の船を上手にコントロールできません。現場に本社の意図・指示が伝わらないのです。この問題を解決するにはさらなる間接管理手法のノウハウを本社が蓄積することが望まれます。
船舶管理とは船会社の機能ですが、大局的に船舶管理というものを見れば、船舶管理を営む船会社は海運業界に存在し、その海運業界は造船業界やメーカーと深く結びついており、さらには保険、代理店、港運、陸運、空運、銀行等多種業界とかかわり合って成り立っています。
これらの海運業や造船業を中心にそれを取り巻く関連産業集団のことを「海事クラスター(Maritime Cluster)」と呼んでいます。ちなみにクラスターとは「ぶとう等の房」の意味です。皆さんもこの「海事クラスター」の一員であることを忘れないで下さい。